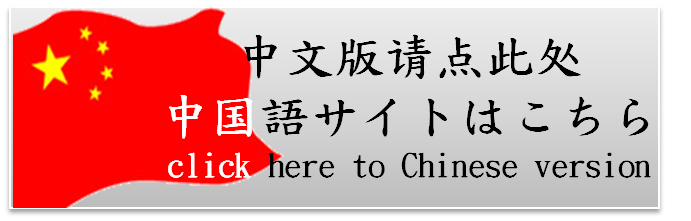- HOME
- 国際離婚ケーススタディ
- 国際離婚ケーススタディ3 日本にいる日本人女性が外国人男性と離婚したいケース
国際離婚ケース3 日本にいる日本人女性が外国人男性と離婚したいケース
 |
|
質問
私は、飛行機の中で知り合った外国人と10年前に結婚し、以後日本で生活しています。私がいうのもなんですが、夫はいわゆるイケメンで、結婚後も女性問題が絶えません。今までは、我慢していましたが、半年以上前に、夫が他の女性のためにアパートを借り、家を出ていってしまいました。ただ、夫は日本にいるようで
|
す。もう我慢の限界で離婚したいと考えています。
外国人と離婚するのは日本人同士の離婚とどう違うのでしょうか。
この点については、「法の適用に関する通則法」(以下「通則法」といいます。)という法律が日本にあり、この法律に基づいてどこの国の法律が適用されるかをまず確定する必要があります。通則法第27条に離婚に関する規定があり、同条は、「第25条の規定は離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は日本法による。」とされています。ちなみに、ここにいう「常居所地とは、人が常時居住する場所で、単なる居所とは異なり、相当長期にわたって居住する場所」とされています。
しかし、相手が離婚に応じなかった場合は、離婚調停の申し立てをし、そこで話しがまとまれば、調停離婚となり話がまとまらず調停が不調となれば、離婚訴訟を提起することになります。
裁判離婚では、離婚原因の有無が争われることになり、前述のように本ケースでは、日本法が準拠法となるので、民法第770条第1項記載の離婚原因(不貞行為、悪意の遺棄、生死が3年以上明らかでないとき、回復の見込みがない強度の精神病、その他の婚姻を継続し難い重大な事由)の有無が審理対象となります。夫の浮気は不貞行為(第770条第1項第1号)として離婚原因となりますので、離婚原因はあるということになります。離婚判決が出て、それが確定すれば、判決正本を役所に提出することになります。ただ、これは日本での離婚の効力であり、夫の本国での離婚の効力については、別途考える必要があります。
たとえば、外国では、アメリカなど協議離婚が認められていない国もありますので、こうした場合には、日本で協議離婚が成立してもアメリカで離婚が成立しません。つまり、日本法が準拠法とされ日本で協議離婚が認められたとしても、夫の本国では日本での協議離婚の効力が認められない可能性があります(それゆえ、夫の本国法の離婚制度について大使館や領事館等に照会してあらかじめ確認しなければなりません。)。
なお、筆者の経験では、家庭裁判所が本国での承認可能性に配慮して、調停調書に「この調停調書は、確定判決と同一の効力を有する。」と付記してくれ、本国で裁判離婚と同様に扱ってくれたことがあり、裁判離婚しか認められない国でも、調停離婚により成立した離婚を有効なものと取り扱ってくれる国もありますので、事前に調査しておく必要があるでしょう。
この点については、最高裁の昭和39年3月25日の判例で、原則として相手方の住所が日本国内にある場合に国際裁判管轄があることになりますが、例外として、相手方が他方の方を遺棄した場合、相手方が行方不明である場合、その他これに準じる場合には、相手方の住所地が日本国内になくても、他方の方の住所が日本国内にあれば国際裁判管轄が認められてきました。平成8年6月24日の最高裁の判例でも、相手方の住所が日本国内にない場合でも、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められています。
ここで重要なことは、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められるか否かは、国籍は関係ないということです。したがって、外国籍同士の夫婦でも、日本に住んでいれば、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められるのです。逆に、日本人同士の夫婦が外国に住んでいる場合に、当然に日本の裁判所に国際裁判管轄が認められるということにはならないので注意が必要です。
本ケースの場合、外国人の夫は、日本に住んでいるということなので、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められるため、日本の裁判所に、調停申立や訴えの提起ができると考えられます。
外国人と離婚するのは日本人同士の離婚とどう違うのでしょうか。
回答
夫婦の一方又は双方が外国人の場合
①離婚の問題についていずれの国の法律に基づいて考えるのかという準拠法の問題
②離婚の方法としてどのような方法を選択すべきか
③相手が離婚に応じないときには日本の裁判所に対して訴えればよいのか
といった国際裁判管轄の問題等が生ずることが通常の日本人同士の離婚と異なります。
①離婚の問題についていずれの国の法律に基づいて考えるのかという準拠法の問題
②離婚の方法としてどのような方法を選択すべきか
③相手が離婚に応じないときには日本の裁判所に対して訴えればよいのか
といった国際裁判管轄の問題等が生ずることが通常の日本人同士の離婚と異なります。
解説
①準拠法の確定
日本人同士の夫婦の離婚の場合、日本の法律が適用されるのは当然ですが、外国人と離婚する場合、まず、問題となるのが、どこの国の法律が適用されるのか、いわゆる準拠法の問題から考えていかなければなりません。
この点については、「法の適用に関する通則法」(以下「通則法」といいます。)という法律が日本にあり、この法律に基づいてどこの国の法律が適用されるかをまず確定する必要があります。通則法第27条に離婚に関する規定があり、同条は、「第25条の規定は離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は日本法による。」とされています。ちなみに、ここにいう「常居所地とは、人が常時居住する場所で、単なる居所とは異なり、相当長期にわたって居住する場所」とされています。
従って、本ケースでは、夫婦の一方である質問者が日本に常居所を有しているので、第27条ただし書により日本法が適用されることになります。ちなみに、第27条が準用する通則法第25条は「夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは、夫婦に密接な関係がある地の法による。」とされています。
本ケースと異なり、質問者の常居所地が日本国外である場合や質問者の国籍が夫と異なる外国籍の場合は、第27条の本文が準用する第25条により、夫婦に密接な関係がある地の法として準拠法が日本法となる可能性が高いと考えられます。
本ケースと異なり、質問者の常居所地が日本国外である場合や質問者の国籍が夫と異なる外国籍の場合は、第27条の本文が準用する第25条により、夫婦に密接な関係がある地の法として準拠法が日本法となる可能性が高いと考えられます。
②離婚の方法
別のところで、離婚には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚があることは述べました。本ケースでも相手が協議離婚に応じるのであれば、双方が離婚届に署名・捺印し、証人2人の署名があれば、離婚届を役所に提出することにより、離婚が成立します。
しかし、相手が離婚に応じなかった場合は、離婚調停の申し立てをし、そこで話しがまとまれば、調停離婚となり話がまとまらず調停が不調となれば、離婚訴訟を提起することになります。
裁判離婚では、離婚原因の有無が争われることになり、前述のように本ケースでは、日本法が準拠法となるので、民法第770条第1項記載の離婚原因(不貞行為、悪意の遺棄、生死が3年以上明らかでないとき、回復の見込みがない強度の精神病、その他の婚姻を継続し難い重大な事由)の有無が審理対象となります。夫の浮気は不貞行為(第770条第1項第1号)として離婚原因となりますので、離婚原因はあるということになります。離婚判決が出て、それが確定すれば、判決正本を役所に提出することになります。ただ、これは日本での離婚の効力であり、夫の本国での離婚の効力については、別途考える必要があります。
たとえば、外国では、アメリカなど協議離婚が認められていない国もありますので、こうした場合には、日本で協議離婚が成立してもアメリカで離婚が成立しません。つまり、日本法が準拠法とされ日本で協議離婚が認められたとしても、夫の本国では日本での協議離婚の効力が認められない可能性があります(それゆえ、夫の本国法の離婚制度について大使館や領事館等に照会してあらかじめ確認しなければなりません。)。
以上のとおり、準拠法が日本法の場合であっても、仮に、夫の本国法が、協議離婚を認めていないのであれば、最初から調停離婚、審判離婚、裁判離婚など協議離婚以外の手続を取る必要があります。
この点、調停離婚・審判離婚も広義の裁判離婚に含まれるとして裁判離婚しか認めない国においても裁判離婚として取り扱ってくれれば調停や審判の申立をする意味がありますが、そうでない場合は、これらの手続で離婚が成立しても意味がないので、最初から裁判離婚の手続をとりたいところです。しかし、日本では、調停前置主義をとっているので(家事事件手続法第257条1項)、原則として、裁判を提起する前に調停の申立てを行う必要があります。
ただ、この点については、本国法があくまでも裁判離婚しか認めない場合には、「当事者の国籍や事案の性質に鑑み、調停に付することが適当でない場合」として、家事事件手続法第257条2項により、調停前置主義の適用を除外することも可能であると言われています。
この点、調停離婚・審判離婚も広義の裁判離婚に含まれるとして裁判離婚しか認めない国においても裁判離婚として取り扱ってくれれば調停や審判の申立をする意味がありますが、そうでない場合は、これらの手続で離婚が成立しても意味がないので、最初から裁判離婚の手続をとりたいところです。しかし、日本では、調停前置主義をとっているので(家事事件手続法第257条1項)、原則として、裁判を提起する前に調停の申立てを行う必要があります。
ただ、この点については、本国法があくまでも裁判離婚しか認めない場合には、「当事者の国籍や事案の性質に鑑み、調停に付することが適当でない場合」として、家事事件手続法第257条2項により、調停前置主義の適用を除外することも可能であると言われています。
なお、筆者の経験では、家庭裁判所が本国での承認可能性に配慮して、調停調書に「この調停調書は、確定判決と同一の効力を有する。」と付記してくれ、本国で裁判離婚と同様に扱ってくれたことがあり、裁判離婚しか認められない国でも、調停離婚により成立した離婚を有効なものと取り扱ってくれる国もありますので、事前に調査しておく必要があるでしょう。
③国際裁判管轄の問題
国際裁判管轄とは、ある事件の申し立てがされたときに、裁判所がその事件について管轄権を持っているか、すなわち、その事件を取り扱うことができるかという問題です。
国際裁判管轄があれば、裁判所はその事件を取り扱うことができますし、国際裁判管轄がなければ、その裁判所はその事件を取り扱うことができず、調停の申立や裁判の提起をしても却下されてしまいます。したがって、国際離婚事件について、調停の申立や裁判の提起をしようとする場合には、まず、その裁判所が国際裁判管轄を持っているかということについて検討しなければなりません。
では、国際裁判管轄とは、どのような場合に認められるのでしょうか。
この点については、最高裁の昭和39年3月25日の判例で、原則として相手方の住所が日本国内にある場合に国際裁判管轄があることになりますが、例外として、相手方が他方の方を遺棄した場合、相手方が行方不明である場合、その他これに準じる場合には、相手方の住所地が日本国内になくても、他方の方の住所が日本国内にあれば国際裁判管轄が認められてきました。平成8年6月24日の最高裁の判例でも、相手方の住所が日本国内にない場合でも、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められています。
ここで重要なことは、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められるか否かは、国籍は関係ないということです。したがって、外国籍同士の夫婦でも、日本に住んでいれば、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められるのです。逆に、日本人同士の夫婦が外国に住んでいる場合に、当然に日本の裁判所に国際裁判管轄が認められるということにはならないので注意が必要です。
本ケースの場合、外国人の夫は、日本に住んでいるということなので、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められるため、日本の裁判所に、調停申立や訴えの提起ができると考えられます。
キャストグローバルにご相談いただく方へ
|
■ご相談の流れ |
| ■お客様の声 |
| ■国際離婚の費用 |
|
■弁護士紹介 |
|
■事務所紹介 |
|
■お問合せ |
|
■アクセスマップ |
国際離婚・国際相続についてお悩みの方は弁護士法人キャストグローバルへ

Copyright (C) 2020 弁護士法人キャストグローバル All Rights Reserved.